「うちの会社って、もしかして“意識高い系企業”なのか?」と疑問に思ったことはありませんか?
ベンチャーや外資系企業にありがちな「英語由来の言葉を多様」や「日本文化に合わない制度設計」などに違和感を感じている人も多いはず。
この記事はそんな人に向けて、以下のような疑問について解説します。
- 意識高い系企業って、どんな特徴があるの?
- 自分の会社は当てはまってる?判断するチェックリストはある?
- そんな社風に、どうやってうまく付き合っていけばいいの?
読めばきっと、「会社に合わせる」以外の選択肢が見えてくるはずですよ!


あなたの会社は意識高い系企業?その特徴とは
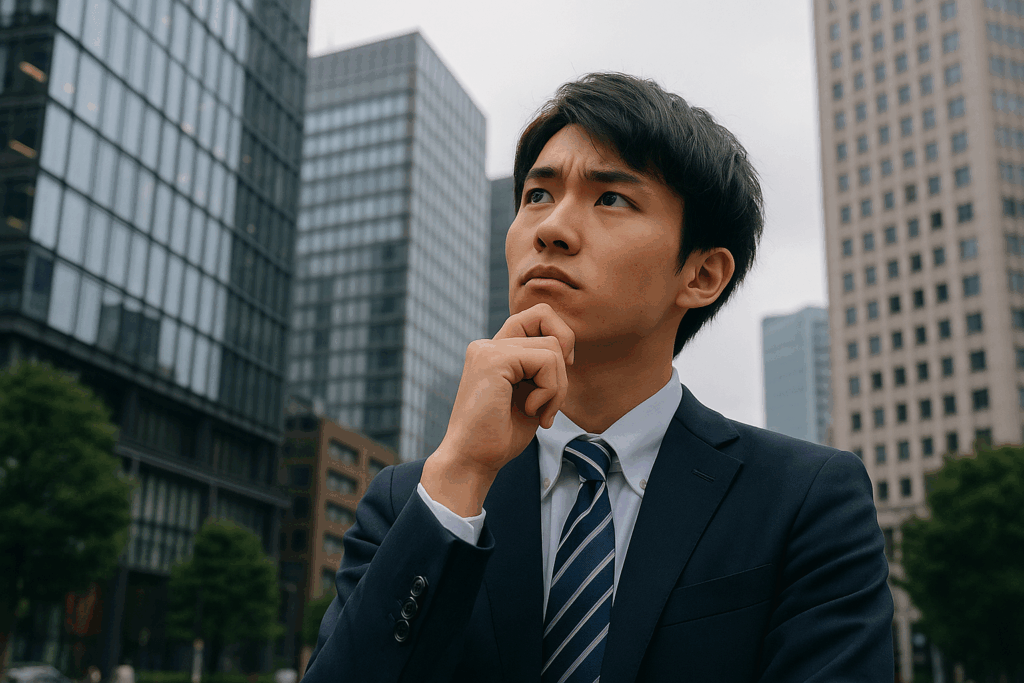
「うちの会社って、もしかして意識高い系…?」と感じたことはありませんか?
最近は、企業文化や社内コミュニケーションにおいて、“意識高い系の要素”が入っている会社も出てきました。
特にIT系やベンチャー企業では、社風や発言のテンションが高めなことも多く、「何となく違和感を感じる人」もいると思います。
そこで本章では以下のポイントを中心に、意識高い系企業の特徴をわかりやすく解説していきます。
- 意識高い系企業とはどういう会社か
- よくある意識高い系企業の特徴10選
- ベンチャーや外資に多い?業種・規模別の傾向
- 社内チャット・会議・用語に潜む兆候
- 企業理念に見る“意識高い”傾向とその背景
それではひとつずつ見ていきましょう!
意識高い系企業とはどういう会社か
「意識高い系企業」の特徴の一つとして、理想やビジョンが社員に浸透しておらず、温度差が生まれてしまっている、というのがあります。
こうした企業は表面上、非常に華やかでモダンな印象を持っています。
たとえば、
- 「社会課題の解決」「未来の働き方」などをミッションに掲げる
- 「英語混じりの社内用語」や「先進的な働き方改革」をアピールする
などです。
上記のような考えが社員に浸透している企業もありますが、問題なのは「それっぽさ」に偏っていて実態が伴っていない場合です。
具体例をあげると、
- 理念は立派なのに毎日深夜残業
- 会議では“心理的安全性”が大事といいつつ、トップダウンで意見が出しにくい
- 海外のユニコーン企業の成功事例を試そうとするが、最後までやりきらない
あなたの勤め先は、大丈夫ですか?
もしここで紹介した事例に近いことが頻繁に起きているようなら、要注意です。
よくある意識高い系企業の特徴10選
意識高い系企業には共通する特徴があります。
悪気がないものも多いですが、言葉や仕組みが独り歩きして社員にプレッシャーを与えてしまうケースが目立ちます。
以下に代表的な特徴を10個、まとめてみました。
- 社内スローガンが英語やカタカナだらけ
- チャットのステータスが「Deep work」「Flow中」など、抽象的なワードを入れる
- 週次の定例会で「内省」や「気づきのシェア」を求められる
- 「心理的安全性」を重視すると言いつつ、本音が言いづらい雰囲気
- なにかと「自己実現」が重視される空気
- 採用ページが「社会課題への挑戦」で埋め尽くされている
- オフィスがコワーキングスペース風で、やたらとおしゃれ
- 「コミュニティ」や「つながり」を強要される社内文化
- 社内報やSNS投稿が全てポジティブで「意識高め」
- 「ワクワク」「ときめき」など、抽象度の高い感情ワードが多用される
こうした特徴が1つ2つ当てはまるだけなら問題はありません。
しかし、いくつも重なると「見せかけ感」や「同調圧力」が強くなって、「なんか疲れるな…」と感じやすくなります。
「こういう文化に馴染めるかどうか」は、自分の価値観を知るいい材料になるので、ぜひ自分の勤め先の状況を確認してみてください!
ベンチャーや外資に多い?業種・規模別の傾向
意識高い系企業は「業種」や「会社の規模」とも関係しています。
特に意識高い系企業が多いのが、IT系やコンサル系のベンチャー企業、そして日本に進出したばかりの外資系企業です。
では、具体例を見てみましょう。
- IT・Web系のスタートアップ
ミッション・ビジョン・バリューを重視し、「社会課題を解決する」など壮大な目標を掲げがち。 - コンサル系企業(特に戦略・人材系)
抽象的なキーワードを日常的に使い、「自己成長」や「変革」が社内文化として根付いている。 - 外資系企業(特に日本進出初期)
海外にある本社の文化をそのまま持ち込むと、日本の価値観とギャップが出やすい。 - 中小の急成長ベンチャー
創業メンバーの思想が強く反映されやすく、「カルチャーへの共感」が求められる傾向が強い。
もちろん、すべてのベンチャー企業や外資系企業がそうというわけではありません。
ただ、組織がまだ未成熟だったり、評価制度が整っていない中で「理念」で押し切ろうとすると、意識高い系っぽさが出やすくなるのは事実です。
自分の職場がどのカテゴリにあたるか、客観的に見てみると面白いかもしれません!
社内チャット・会議・用語に潜む兆候
日々の社内チャットや会議中の言葉づかいには、その会社が意識高い系かどうかのヒントが、たっぷり詰まっています!
もし、以下のようなワードや空気が飛び交っていたら、ちょっと注意して観察してみましょう。
- 「パーパス」「アジェンダ」「コミット」「エンゲージメント」
- 「ナレッジ共有」「アウトプットファースト」「PDCAをまわす」
- 「心理的安全性」「リスキリング」「レバレッジ」「ラーニング」
- SlackやTeamsでのステータスが「Deep work中」「Flow中」など抽象的
- 最後に「今日の気づきや学びを一言ずつ」コーナーがある
- KPIや売上といった数字の話より、価値提供やビジョンの話に時間が割かれる
- 会議の進行役が「話しやすい場づくり」に異常にこだわる
もちろん、これらの言葉や行動がすべて悪くはありません。
でも、「誰かが使っているから」と無理に合わせていると、どこかでモヤモヤがたまることも。
「この言葉、本当に必要?」と一度立ち止まって考えるだけで、精神的な疲労感がグッと減るかもしれません。
企業理念に見る“意識高い”傾向とその背景
企業理念(ミッション・ビジョン・バリュー)が抽象的で理想論的な場合、意識高い系企業の可能性があります。
早速、具体的な例を見ていきましょう。
- 「テクノロジーで世界に幸せを」
- 「誰もが自己実現できる社会の実現」
- 「ワクワクする未来を共創する」
- 「社員一人ひとりが主役の組織へ」
ぱっと見は素敵な言葉たちですよね。
でも、現実が伴っていないと、「きれいごとだけで中身がない」と社員が不信感をいだくことになります。
では、なぜこうした企業理念が多いのでしょうか?
その背景には、スタートアップや若手経営者による「ビジョンドリブン経営」が流行していることがあります。
また、採用やPRの面でも、“社会性”や“先進性”を打ち出すとイメージが良くなりやすいため、理念がどんどん抽象化・理想化されがちです。
社員がその理念に共感し、自発的に行動できているなら問題ありません。
一方で「企業理念に合わせること」が目的化していたり、「実態とズレすぎていて現場がしらけている」なら、それは危険信号です。
いますぐ見直さないと意識高い系企業になってしまう可能性がとても高い状態といえるでしょう。
理念は“見せるもの”ではなく、“活かすもの”。そう考えると、自分の会社がどうか、冷静に判断しやすくなるはずです!
意識高い系企業との上手な付き合い方

「正直、しんどい…けど辞めるほどじゃないし」そんな気持ちで日々会社に行っていませんか?
ここでは、そんなあなたが無理せず働き続けられるよう、実践しやすいコツを紹介します!
- 距離感を保ちつつ乗り切るメンタル術
- 合わせすぎず孤立もしない立ち回り方
- “空気”に巻き込まれないための戦略
- 疲れたときの対処法と自分らしさの保ち方
会社の空気に疲れてしまう前に、ぜひ試してみてください。
距離感を保ちつつ乗り切るメンタル術
メンタルを守るためには、“行動”と“共感”を切り離すことが重要です!
たとえば、周囲が「このnote最高でした!」と盛り上がっていても、あなたまで無理に共感する必要はありません。
「いいね」押すという行動はとっても、気持ちは同調しない。それでOKなんです。
メンタルを守るには、自分の価値観を見失わずに、「立場や役割として最低限やるべきこと」だけをこなすのがコツ。
まじめで優しい人ほど同調圧力に飲み込まれやすいので、「ちょっと冷めた目線」くらいがちょうどいいですよ!
合わせすぎず孤立もしない立ち回り方
意識高い系企業で働いていても、意識高い系企業の空気に完全に染まる必要はありません。
でも、社内の空気に合わせないで孤立してしまったら、働きづらくなりそうで不安…という人も多いですよね。
そんな人におすすめしたいのは、「話を聞きつつ、過度に乗らない」中間ポジションです。
たとえば、
- 会議では一言二言、前向きなリアクションを入れる
- 社内チャットでは「共感風のコメント+スタンプ」でやり過ごす
- 自分の価値観に反する案件には、やんわり距離を置く
このように、空気を読んで反応しながらも、全てに付き合わない姿勢がカギです。
上記の内容を参考に、自分にとって「ちょうどいい距離感」を探ってみてください!
“空気”に巻き込まれないための戦略
職場の“空気”が重たく感じるとき、その原因はもしかしたら「同調圧力」かもしれません。
同調圧力なんて簡単に無くならないでしょ…と思っている人も安心してください。
同調圧力が無くならなくても、個人でできる対処法はあります!
その対処法は、「空気を客観視する視点」を持つことです。
具体的な対処法としては、
- 社内チャットや会話を“分析対象”として眺めてみる
- 違和感を感じたら無理に共感せず、「違和感」としてメモする
- 「今日は1回だけ合わせる」と自分ルールを決める
このように社内に流れる空気を「俯瞰して見る」ように意識するだけで、驚くほど気持ちが楽になりますよ!
疲れたときの対処法と自分らしさの保ち方
意識高い系企業で働くのに疲れてきて「もう限界かも…」と感じたら、転職を考える前に“気持ちのリセット”をしてみましょう。
以下のような小さな工夫で、気持ちを切り替えることができますよ!
- カフェや公園など、会社の空気から離れた場所で一人時間を持つ
- あえてB級映画や漫画のような“意識が低い趣味”に没頭してみる
- 「自分ってどんな働き方が心地よいのか?」をノートに書き出す
疲れを感じたときほど、自分自身の感覚を取り戻すチャンスです。
意識高い系企業で働いていても「周りと同じじゃなくて」と思えることが、心の余裕につながります!
転職すべきか迷っている人の判断ポイント
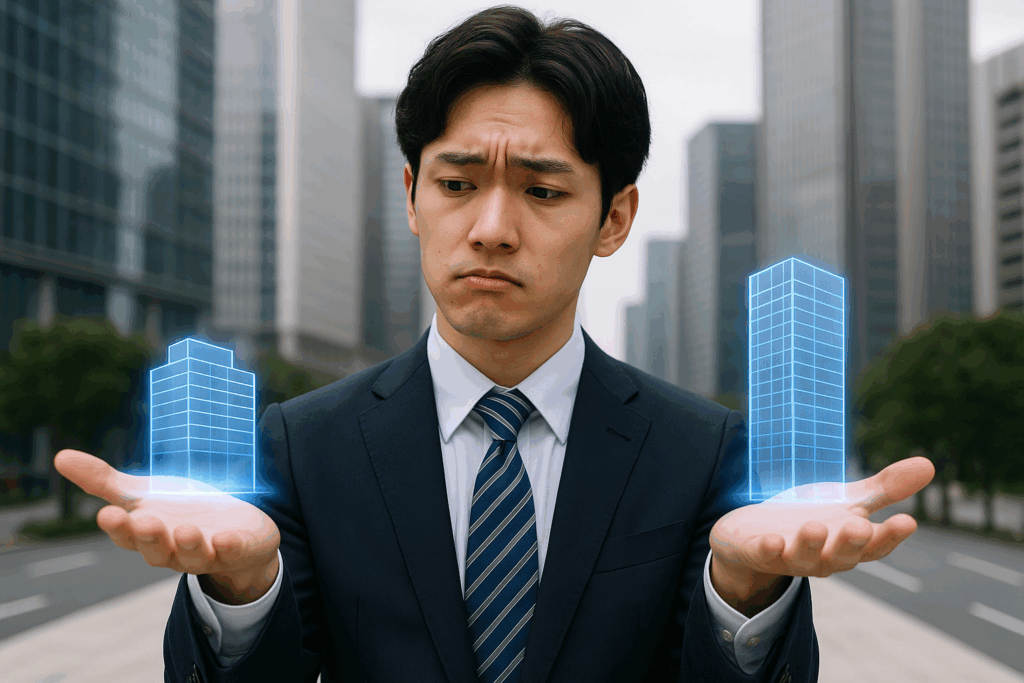
意識高い系企業に勤めていて、「今の会社で頑張るべき?それとも転職したほうがいいのかな?」とモヤモヤしているあなたへ。
本章では、意識高い系企業から転職しようか迷ったときの考え方を解説します。
- 意識高い系企業が向いている人・向いていない人
- 転職前に考えるべき3つのこと
- 社風に違和感を感じた時の選択肢とは
- 「意識高い系企業を辞めたあとどうなる?」のリアルな声
焦らず、冷静に自分の選択肢を見つめ直してみましょう!
意識高い系企業が向いている人・向いていない人
結論から言えば、「意識高い系企業の文化にワクワクできるかどうか」が分かれ目です!
向いている人はこんなタイプ。
- 自己実現や社会貢献への意識が高い
- 新しい価値観やワードを柔軟に受け入れられる
- 抽象的な目標にも自分なりの意味づけができる
逆に、向いていない人は、
- 明確な評価基準や具体性を求めるタイプ
- 本音と建前の使い分けが苦手
- 「自分らしさ」を重視したい人
自分がどちら寄りかを見極めることで、今後の判断がグッとラクになります。
もし、「意識高い系企業で働いてるんだ(笑)」のような、周囲からの評価を気にして転職を考えている人は、一度冷静に考えてみてください。
気づいていないだけで、意識高い系企業はあなたに向いている会社かもしれません。
転職前に考えるべき3つのこと
転職を考え始めたとき、いきなり求人を見るのはNGです!
まずは以下の3つを自分に問いかけてみてください。
- 今の会社で得ているスキルや経験は何か?
- 本当に辛いのは“仕事”か、“職場の雰囲気”か?
- 転職になにを求める?(例: 安定 / 成長 / 裁量など)
この整理ができていないと、転職活動がうまくいかない可能性が高くなります。
また、運良く転職できても次の職場で同じ悩みを繰り返すかもしれません。
転職は「今の自分をもれなく棚卸しできたか」が、重要なポイントになります。
焦らずに自分と向き合うようにしましょう!
社風に違和感を感じた時の選択肢とは
「会社になんか馴染めないから辞めようかな…」
そんな考えにとらわれてしまったときの選択肢を紹介します。たとえば、
- 異動(部署変更や勤務地変更)を検討してみる
- 信頼できる先輩や同僚に率直に相談する
- 馴染めないと感じたときの状況を書き出して対処法を考える
「合わないから辞める」と決断するより先に、「いまの会社で合うところを探す」という選択肢があります。
社風に違和感を感じられるということは、感性が鈍っていない証拠です。
その気づきを大切にして、自分にとって最良の選択ができるよう、行動してみてください。
「意識高い系企業を辞めたあとどうなる?」のリアルな声
「意識高い系企業を辞めたら楽になった」という声がある一方、「意識高い系企業を辞めてから、そんなにわるくなかったと気づいた」という意見もあります。
例えば、「辞めてよかった」という意見の場合は、

自分らしく働ける環境に移ったことで、やっと肩の力が抜けた。
前職の“文化”に違和感を持っていたのは、ちゃんと意味があったんだと気づけた。
逆に、「意識高い系企業もそんなにわるくない」という意見だと、

辞めたあとに気づいたのだけど、意識高い系企業で働いていたときはチャレンジすることが当たり前で、それが成長につながっていた。
といった感じです。
このように、どんな選択にもメリットとデメリットがあります。
大事なのは「自分で納得して選ぶこと」です。それが、後悔のないキャリアにつながります!
意識高い系企業に入る前に知っておくべきこと

就活や転職活動中、「この会社、やたらとキラキラしてるけど本当に大丈夫?」と感じたことはありませんか?
本章では、意識高い系企業に入る前にチェックしておきたいポイントをまとめました。
- 就職・転職活動中に見抜くポイント
- 面接で出る“意識高いキーワード”の例
- 企業理念やビジョンの読み解き方
- 情報収集に使えるSNSや口コミサイト
入社後に「思ってたのと違う!」とならないためにも、事前チェックが重要です!
就職・転職活動中に見抜くポイント
結論から言えば、「企業が掲げている理想」と「実態」のバランスを見ることがカギです!
最低限、以下のような視点は持っておきましょう。
- 採用ページが過度に理想論だけで構成されていないか?
- 社員紹介に細かな仕事内容が書かれているか?
- 求人内容と会社のSNSで発信されている内容にズレはないか?
SNS上で洗練されて見えたり先進的に見えたりしても、実態がともなわない会社はたくさんあります。
不確かな情報に惑わされず、等身大の会社像を探る目を養いましょう。
もし一人で判断するのが難しいと感じた場合は、転職エージェントや口コミサイトを使ってみてください。
あなたの欲しい情報に出会えるかもしれませんよ!!
面接で出る“意識高いキーワード”の例
面接中に「この会社、意識高い系かも?」と気づくヒントはあります!
たとえば、こんな言葉が頻出していたら、意識高い系企業の可能性大です。

我々のパーパスは〜

〇〇ドリブンで物事を捉えてます!

カルチャーフィットを重視していて〜

“らしさ”を大切にする組織です。
もちろん、会話のなかでこうした言葉が出ることもあるでしょう。
一方で、こうした言葉が繰り返し使われるようなら、それらの言葉や言い回しが“その会社の文化”として定着している可能性大です。
意識高い系企業に入りたくないと思っている人はもちろん、入りたいと思っている人は、ぜひ日常的に使われている言葉に注目してみてください。
企業理念やビジョンの読み解き方
「理念が素晴らしい=いい会社」とは限りません。
大切なのは、以下のポイントを押さえて理念を“現実と照らして読む”ことです!
- 理念が抽象的すぎて具体的な実行計画が見えない場合は注意
- 「誰に対して、どんな価値をどう届けるか」が明確か?
- ミッションと日々の業務が地続きであるように感じられるか?
理念は会社の顔ですが、その表情の裏にある“現場の温度”まで読み取るのは至難のわざです。
そこで、おすすめしたいのが「気になる企業そのものや、同業他社で働いている知人や友人に聞いてみること」です。
聞く内容は、業界の中での立ち位置や働き方の傾向など、気になっていることであれば何でも構いません。
きっと転職エージェントや口コミサイトでは得られない情報にアクセスできるでしょう。
もしそういった知人や友人がいない場合は、転職エージェントや口コミサイトを活用してみてください!
情報収集に使えるSNSや口コミサイト
一番リアルな情報は“公式サイトの外”にあります!
とくに以下のツールは、企業文化や社内の雰囲気を探るのにとても役立ちます。
- X(旧Twitter):元社員・現役社員の発言を要チェック
- OpenWork & 転職会議:社員の口コミが満載
- Wantedly:採用コンテンツに企業の価値観がにじみ出ている
SNSは主観が混ざるので盲信はNGですが、“気づき”のヒントに出会うことができます。
以下にそれぞれのサービスのリンクを載せておくので、ぜひ確認してみてください!
まとめ
今回は、「意識高い系企業の特徴と上手な付き合い方」というテーマについてお話ししました。
最近は「パーパス」「ジョブ型雇用」などのカタカナ語が当たり前に飛び交い、その雰囲気に違和感を覚える方も多いと思います。
そんなときに特に知っておきたいのが、今回紹介した以下の観点です。
- 距離感を保ちつつ乗り切るメンタル術
- 合わせすぎず孤立もしない立ち回り方
- “空気”に巻き込まれないための戦略
- 疲れたときの対処法と自分らしさの保ち方
また、意識高い系企業から転職を考えている人に向けて、以下も解説しました。
- 意識高い系企業が向いている人・向いていない人
- 転職前に考えるべき3つのこと
- 社風に違和感を感じた時の選択肢とは
- 「辞めたあとどうなる?」のリアルな声
本記事では、無理に意識高い系企業の文化や理念に染まるのではなく、自分のペースで周囲と付き合う方法を中心にお伝えしてきました。
勤め先に違和感を感じたときに、この記事の内容をふと思い出して、自分の働き方を見直すきっかけにしてもらえたらうれしいです!


