「部下の発言がちょっと空回りしてて意識が高い系っぽくなってる…。」
「でも“意識高い系”って直接は言いづらいんだよな」
職場でそんなモヤモヤを抱えたことはありませんか?
“意識が高い”こと自体は素晴らしいのに「意識高い系」と受け取られてしまうと、どうしても皮肉っぽく聞こえてしまいますよね。
そこで本記事では、
- 「意識高い系」と「意識が高い人」の違いって何?
- 気まずくならずにやんわり伝えるには?
- 自分が“意識高い系”に見られないためには?
など、空回りしている部下への伝え方や関わり方に悩む方に知ってほしい内容を丁寧に紹介します。
今日から使える表現やマネジメントのコツが満載です。ぜひ、最後まで読んでみてください!


「意識高い系」の意味と誤解されやすい理由
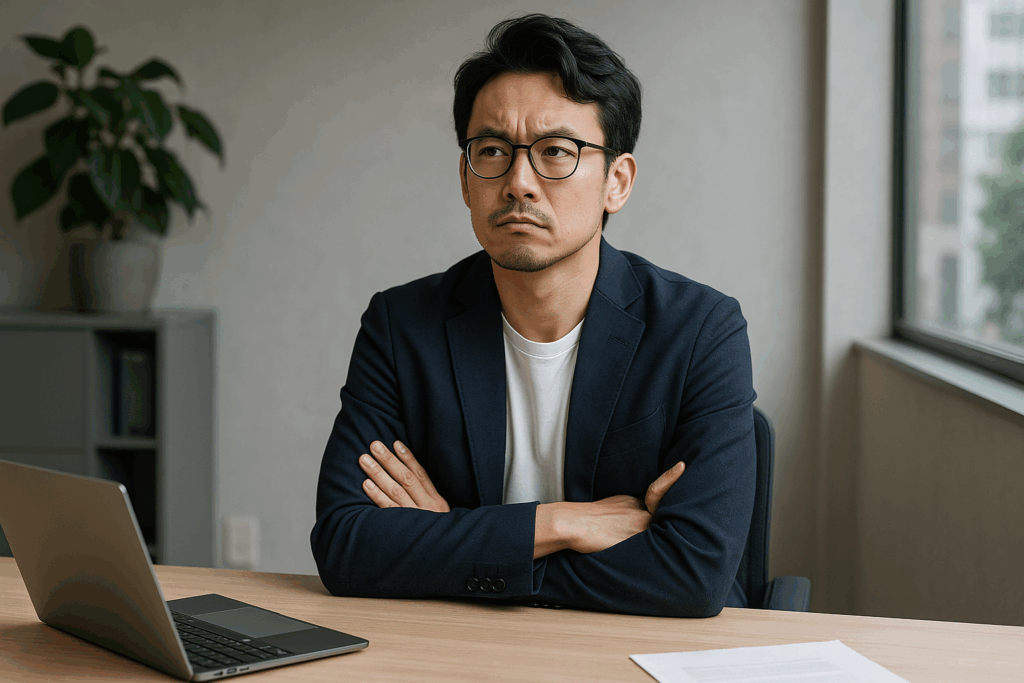
「意識高い系と言われてバカにされている気がする…」そんなふうに感じること、ありませんか?
“意識が高い”ことはポジティブな意味を持っているのに、似た言葉の“意識高い系”はなぜネガティブな言葉になってしまったのでしょうか。
この章で取り上げるのは、以下のとおりです。
- 意識が高い人と意識高い系の決定的な違い
- なぜ「意識高い系」は揶揄されやすいのか
- 職場でよく見かける「意識高い系」あるある
あなた自身が意識高い系と誤解されないためにも、まずはこの違いと背景を正しく理解しておきましょう!
意識が高い人と意識高い系の決定的な違い
まず最初にお伝えしたいのが、「意識が高い人」と「意識高い系」は言葉が似ているだけで全く違う存在です!
意識が高い人は、周囲に配慮しながらも着実に行動を重ねて成果を出すタイプ。
一方で意識高い系は、見せかけの努力や言葉ばかりが先行し、実績や行動が伴っていません。
たとえば、毎週のように「週末は◯◯のセミナーに行ってきました!」とSNSでアピールしていても、仕事の成果はいまひとつ……。
そんな状態が続くと「アピールしたいだけの意識高い系」として、周囲から煙たがられてしまう要因になります。
週末にセミナーに参加すること自体は勉強熱心で素晴らしいことです。
しかし、セミナーで学んだことを実践して成果に結びつけられていない場合は、SNSで過度にアピールしない方がよいでしょう。
なぜ「意識高い系」は揶揄されやすいのか
「意識高い系」が揶揄されやすいのは“頑張っている自分に酔っている”ように見えるからです。
努力をアピールしたい気持ちは理解できます。
しかし、周囲の空気を読まずに語りすぎたり、成果より発言が先走っていたりすると、“鼻につく存在”になってしまいがち。
特にビジネスの現場では、「結果が重視される傾向」が強く、発言や行動に“中身”が伴っていないと、

また”意識高い系”か…
と心の中でツッコまれてしまう可能性も。
自分を客観視できるバランス感覚を持ってこそ、本当の意味で“意識が高い人”として評価されるのです。
なお、意識高い系についてより詳しく知りたい方は、以下の記事も読んでみてください!

職場でよく見かける「意識高い系」あるある
あなたの周りにも、こんな人いませんか?
- 毎朝「最近読んだ自己啓発本」を話題に出す
- 横文字、カタカナ語を多用しすぎて伝わらない
- SNSで「学び」「気づき」を頻繁に投稿
- やたらと「変化」や「成長」に反応する
もちろん、学んだことを発信するのは悪いことではありません。
しかし、それが“口先だけで行動していない”と、「意識高い系だな…」という印象になってしまうのです。
重要なのは、“実際に何をしているか”。
周囲への発言と行動が一致していれば、自然と信頼が得られるでしょう。
また、「意識高い系あるある」については、以下の記事に詳しくまとまっていますので、ぜひ読んでみてください!

【状況別】意識高い系の言い換え実例と使い方

どんなに良い言葉でも、使うタイミングを間違えると逆効果です!
ここでは、実際のシーンごとに「意識高い系」をやんわり言い換える具体例を紹介します。
- シーン1:部下の過剰アピールをやんわり指摘する
- シーン2:会議で空回りする発言をサポートする
- シーン3:SNSでの“意識高い投稿”を見たとき
信頼されるリーダーには、場面に応じた対応力が欠かせません!
本章を熟読して、ぜひ日々の業務に活かしてくださいね!
シーン1:部下の過剰アピールをやんわり指摘する
結論から言うと、「熱心さ」を活かす方向に話を持っていくのがベストです!
たとえば、報告のたびに“学び”をアピールしてくる部下には、

熱心ですごくいいね。
次はその学んだことを、“どう成果に結びつけたか”を報告してほしいな。

その学ぼうとする精神、応援してるよ。
ただ、新しいことを学ぶペースは少しおとして、これまで学んだことを実践する時間を作るのもアリかもね。
といった形で、相手の努力を肯定しながら進む方向の修正をうながしましょう。
努力アピールを否定するのではなく、「伝え方」を見直す姿勢が大切です。
シーン2:会議で空回りする発言をサポート
会議中、部下の意識の高さは伝わってくるけど、内容が的外れ……そんな時は「ひろって伸ばす」対応が有効です!
例えば、

そのアイデアいいね。
ただ、いまの会話の流れとは少しズレてる感じがするから、別の機会に深掘りしてみようか。

それ、いま話しているAのプロジェクトじゃなく、Bのプロジェクトで試してみるのはどう?
というように、“否定せずに次のチャンス”につなげてあげるイメージです。
リーダーのさじ加減ひとつで、「意識高い系」が「頼れるチャレンジャー」に変わるかもしれません!
シーン3:SNSでの“意識高い投稿”を見たとき
SNSで部下の「#学び」や「#インプット」にあふれた投稿を見ると、「またか…」と感じてしまうこと、ありますよね?
けれど、それらの投稿は“学びたい”というエネルギーを発散した結果でもあります。
そこで、面談の場などを利用して、

○○さんの投稿、前向きですごくいいね!
と一度認めたうえで、

その学びが今後の成長にどうつながるか期待しているよ。
と未来に視点を移しましょう。
SNSでの発信は“外向き”の行動で、上手にアピールすれば信頼を得られるように感じますよね。
しかし、信頼はコツコツと積み上げるような“内向き”の行動に宿ります。
そこに気づいてもらえるようサポートをすることが、上司の大切な役割です。
伝え方とマネジメント:やる気を活かす接し方

意識高い系に見える行動の裏には、たいていの場合「成長したい」「認められたい」という気持ちがあります。
その芽を摘まずに、どう伸ばしていくか。それがマネジメントの腕の見せ所です!
- 相手の成長意欲を潰さない関わり方
- 「意識高い系」と言わずに行動を促す言葉
- フィードバックで信頼を得る3つのポイント
正しい伝え方ができれば、チーム全体の雰囲気もグッと良くなります。
マネジメント層の方は、ぜひ本章を熟読してみてください!
相手の成長意欲を潰さない関わり方
あなたの部下が「また変なこと始めたな」と思っても、いきなり否定しないで「努力の方向性」を一緒に整えてあげてみましょう。
「それ、どんな目的でやってるの?」と関心を持って接するのがコツです。
多くの若手社員は「自分の行動に自信が持てないまま」頑張っています。
だからこそ、「君の挑戦、すごくいいと思うよ」と一言添えるだけで、やる気が湧いて意欲的に業務に取り組むようになるでしょう。
リーダーが“話を聞いてくれる人”になれば、部下も自然と学ぶ力を伸ばしていきます。
「意識高い系」と言わずに行動を促す言葉
部下の言動をみて「意識高い系かよ」と感じても、その言葉は封印して代わりに、次のような“うながしフレーズ”を活用しましょう。

その考え方、前向きでいいね。次は実践で見てみたいな。

その熱意、チームに活気が出そう。でも今はここに集中しようか。

チャレンジ精神があっていいね。結果も楽しみにしてるよ!
部下が「あれ?」と思う言動をとっても、まずは褒められるポイントを探して褒める。
その後で、して欲しい行動をうながしてみましょう。
こうした表現は、“あなたを認めている”というメッセージを含みつつ、具体的な期待を伝えることができます。
目的は、やる気を否定せずに“軌道修正”することです。
「褒めポイント探し」はチーム全体にも良い影響が期待できるので、ぜひ実践してみてください!
フィードバックで信頼を得る3つのポイント
信頼されるフィードバックには、共通する3つのポイントがあります。
それぞれ個別に使ってもよいのですが、3ステップで使うとより効果的です。
- 事実に基づいて褒める
例:昨日の会議で提案してくれた新企画、よかったよ。と、事実に基づいて褒める。 - 改善の余地を明確に伝える
例:もう少しシンプルに伝えたら、もっと刺さると思う。と、なおすと良くなるポイントを具体的に伝える。 - 未来志向で終わる
例:次もまた、期待してるね!と、期待していることを伝える。
この3ステップで伝えれば、「ちゃんと見てくれてるんだ」と部下も納得しますし、「次もがんばろう」と思ってくれます。
相手を育てながら信頼関係も深まる、一石二鳥の方法です!

自分が「意識高い系」と思われないために

リーダー自身も無意識に“意識高い系っぽく”なっているかもしれません!
本章では、知らずにやってしまいがちな「意識高い系な行動」や、信頼される「自然な意識の高さの保ち方」をお伝えします。
- 無意識のうちにしていない?要注意な行動
- 周囲に信頼される“自然体の意識の高さ”とは
自分を振り返ることは、チームを整える第一歩でもあるんです。
無意識のうちにしていない?要注意な行動
まず知っておきたいのが「知識や経験の共有をしすぎると、意識高い系に見える」ことです。
たとえば、
- 「◯◯で学んだことを、さっそく実践してみたんだけどさ…」と頻繁に共有
- 「最近の気づきなんだけど…」というフレーズで話し始めがち
- 知識をひけらかすような会話が増えてきた
こんな言動、していませんか?
もちろん成長意欲は大切ですが、相手との温度差を無視すると、“押しつけがましい人”になってしまいます。
意識の高さをアピールするよりも、「どう受け取られるか」を考えるほうが、はるかに“意識が高い”ことなんです!
周囲に信頼される“自然体の意識の高さ”とは
「本当に信頼される意識が高い人」は、自己アピールより“行動”で語ります。
- 静かに努力して、結果で示す
- 必要なときにだけ発言し、あとは聞き役に回る
- 他人の成果を素直に認められる
こうした態度や行動が周囲の信頼を集め、「あの人、ちゃんとしてるよね」と評価される要因になります。
「べらべら語るより、とにかく実践すること。」
それが、“意識高い系”と“意識が高い人”の最大の違いなのです。
まとめ
「意識高い系」と言われることに誰もが少し敏感になってしまい、「努力している」と言い出しにくい現代。
しかし、そんな状況でも「成長したい」「変わりたい」という前向きな気持ちを持った若者がいることを、理解できたのではないでしょうか。
だからこそ、若者に対する“言葉選びと接し方”が大切なのです。
この記事を通じて、あなたのチーム運営がよりスムーズに、そして建設的になることを願っています。
まずはひとこと、「その挑戦、いいね!」と伝えるところから始めてみてはいかがでしょうか?



